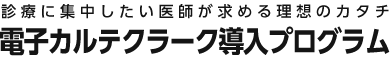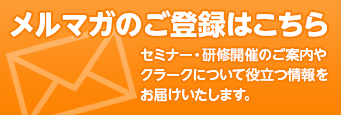生活習慣病管理料の算定のポイント
令和6年度診療報酬改定で「特定疾患療養管理料」の対象疾患から生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)が削除されたことを受けて、生活習慣病患者の管理は、「生活習慣病管理料」に一本化されました。また、生活習慣病管理料についても、従来の点数が生活習慣病管理料(Ⅰ)に、特定疾患療養管理料の受け皿として、生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されています。
生活習慣病管理料→(新)生活習慣病管理料(Ⅰ)
1脂質異常症を主病とする場合 610 点
2高血圧症を主病とする場合 660 点
3糖尿病を主病とする場合760 点
※検査等を包括する場合
特定疾患療養管理料→(新)生活習慣病管理料(Ⅱ)
脂質異常症、高血圧症、糖尿病共通 333点
※検査等を包括しない場合
特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料の違い
このような制度変更に伴い、どのような問題が生まれているのでしょうか。そもそも特定疾患療養管理料の算定要件は、「特定疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定できる」もので、「管理内容の要点をカルテに記載する」ことが求められています。わたしもクラーク研修などで、特定疾患療養管理料を算定する際は、カルテのP(計画)欄に必ず指導コメントを記載するよう説明してきました。
一方で、生活習慣病管理料の算定要件は、「生活習慣病を主病とする患者に対して、患者の同意を得て治療計画を策定し、治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定」できます。管理については、「服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨を患者に対して『療養計画書』により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の署名を受けた場合に算定できる」としています。
特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は、算定プロセスが大きく異なるのです。特定疾患療養管理料が管理内容の要点をカルテに記載することで算定できるのに対し、生活習慣病管理料は、「療養計画書」を作成し、患者へ説明し、患者の「署名」が必要となるのです。つまり、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料の算定変更に当たってクリニック側の手間が大幅に増加するのです。この変更部分をいかに効率化するかが、算定を進める上でのカギと言えるでしょう。
ポイント1 療養計画書の作成を事前アンケートで効率化する
療養計画書の作成を効率化するポイントは、患者と相談して決める必要がある「達成目標」と「行動目標」をいかにスムーズに定めるかにあります。この目標設定については、その場で患者に決めてくださいというのも難しいところであり、決定プロセスに時間を要しますので、事前にアンケートを取るなどして療養計画書作成のための準備を行うことが有効です。
その際、目標の目安となる文言をあらかじめ提示し、選択してもらうことで、患者は目標を決定しやすくなると考えます。課題を明確にし、課題解決のアプローチとして、達成目標と行動目標の関係をしっかりとアンケートを通して患者に伝えることになります。
ポイント2 患者同意のサインは場所と担当を工夫する
療養計画書ができたならば、患者同意のサインが必要になります。このサインについては、疑義解釈において、医師以外のスタッフが診察室外で行うことが認められています。そこで、診察室で医師やクラークが行う方法に加え、処置室で看護師が行う方法、事務が会計時に行う方法などのバリエーションが考えられます。スタッフとよく相談して、【どこで】【誰が】行うのが最も効率的なのかを話し合うと良いでしょう。
ポイント3 継続の療養計画書の作成タイミングをメモ欄に記載する
療養計画書は、「おおむね4か月に1回」の作成が必要になります。この4か月に1回という頻度は忘れやすいため、作成時期の管理が重要になります。例えば、6月1日に初回の療養計画書が作成された場合、4か月後の療養計画書は10月1日となりますので、その日付をカルテのメモ欄に書いておき、忘れずに療養計画書を発行するようにすると良いでしょう。その際、カルテを毎回開いて確認するのではなく、患者の受付一覧で確認できるところに残すことで手間が減ると思われます。
また、来院頻度が毎月、2か月1回であれば問題ないのですが、3か月に1回の場合は、「おおむね」という文言は目途と読み替えることができるので、3か月後に発行することでも構わないと思います。
ポイント4 制度変更について患者に事前に説明する
今回の制度変更の内容について患者の理解を得られなければ、患者のサインをスムーズに取得することは難しいと考えます。そこで、待合室のモニターやポスターなどで、今回の制度変更の趣旨を明示しておくことも必要です。
今回、厚労省は今後の生活習慣病患者の増加を予測し、制度変更が必要と考え、従来よりもより強固な管理を求めています。これは医師と患者が自らの病気について話し合い、相互理解の上に治療を進めるSDM(Shared Decision Making)の考えに則っています。
※SDMとは、「質の高い医療決断を進めるために、最善のエビデンスと患者の価値観、好みとを統合させるための医療者と患者間の協働のコミュニケーション・プロセス」のことです。